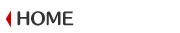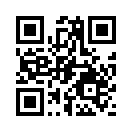【25.08.31】NO.2287 「高齢者が健康で安心して生活できる地域共生社会の実現」めざす提言書を市長に提出
「終活相談窓口の設置」「補聴器購入支援制度の創設」など4つの柱からなる政策提言
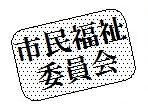 市民福祉委員会(兼子義信委員長)6名は8月20日、「高齢者が健康で安心して生活できる地域共生社会の実現」のための政策提言書を石川智子市長に提出、佐藤おさむ議員も副委員長として参加しました。提言は、「本市ではこれまでも高齢者福祉に取り組んできたが、課題の質や規模の変化に対応するためには、さらに一歩踏み込んだ施策が求められている」とし、4つの柱からなる政策提言をまとめました。以下、提言内容をお知らせします。
市民福祉委員会(兼子義信委員長)6名は8月20日、「高齢者が健康で安心して生活できる地域共生社会の実現」のための政策提言書を石川智子市長に提出、佐藤おさむ議員も副委員長として参加しました。提言は、「本市ではこれまでも高齢者福祉に取り組んできたが、課題の質や規模の変化に対応するためには、さらに一歩踏み込んだ施策が求められている」とし、4つの柱からなる政策提言をまとめました。以下、提言内容をお知らせします。
【提言1】 終活相談窓口の設置
 市民が安心して人生の終盤を迎えるため、法的・生活的課題に幅広く対応する「終活相談窓口」を総合福祉センター等に設置する。相続・遺言・身元保証・死後事務・家財整理・孤独死対策など、個別性の高い相談に対し、弁護士・司法書士・社会福祉士等の外部専門職と連携し、実効性ある支援を行う。
市民が安心して人生の終盤を迎えるため、法的・生活的課題に幅広く対応する「終活相談窓口」を総合福祉センター等に設置する。相続・遺言・身元保証・死後事務・家財整理・孤独死対策など、個別性の高い相談に対し、弁護士・司法書士・社会福祉士等の外部専門職と連携し、実効性ある支援を行う。
【提言2】介護人材「リスタート支援金制度」創設
 市内の介護有資格者や離職経験者が再び現場に復帰することを促進するため、一定期間の継続勤務後に支援金を支給する制度を創設する。市内介護事業所へのマッチング支援とあわせて、即戦力人材の活用と定着を図る。
市内の介護有資格者や離職経験者が再び現場に復帰することを促進するため、一定期間の継続勤務後に支援金を支給する制度を創設する。市内介護事業所へのマッチング支援とあわせて、即戦力人材の活用と定着を図る。
【提言3】買い物弱者対策としての移動販売支援
移動手段の制約を受けやすい高齢者に対し、民間スーパー等による移動販売車の導入を支援する。地域の町内会や自治会、福祉団体と連携し、定期巡回の拠点づくりや住民周知を進め、安定した食料・日用品の供給と見守り機能を強化する。
【提言4】補聴器購入支援制度の創設
 加齢性難聴により孤立や認知機能低下が懸念される高齢者に向けて、市独自の補聴器購入補助制度を創設する。医師の診断を条件に、所得制限を設けた上で65歳以上の高齢者を対象に助成を行い、医療機関・認定販売店と連携して適正かつ効果的な支援を推進する。
加齢性難聴により孤立や認知機能低下が懸念される高齢者に向けて、市独自の補聴器購入補助制度を創設する。医師の診断を条件に、所得制限を設けた上で65歳以上の高齢者を対象に助成を行い、医療機関・認定販売店と連携して適正かつ効果的な支援を推進する。
本提言は、「行政・地域・民間が一体となり、誰もが安心して老後を迎えられる持続可能な共生社会の実現に向けて、柔軟かつ力強い制度設計をお願いしたい」と述べています。
応対した、石川市長並びに松永副市長からは、「今までも提言で実現したものがあり、よく検討したい」旨の感想が寄せられました。
トイレのジェンダーギャプ解消へ 日本共産党の質問で国が動き出す
 駅や空港、商業施設、公共施設などの女性トイレに長時間待ちの行列ができる問題で、政府は24年7月9日、改善に向けた関係府省連絡会議を初開催。トイレ設置数の基準の点検・見直しを進めることなどを確認し、大規模イベントで女性用仮設トイレの十分な確保などを求める通知を主催者に発出。
駅や空港、商業施設、公共施設などの女性トイレに長時間待ちの行列ができる問題で、政府は24年7月9日、改善に向けた関係府省連絡会議を初開催。トイレ設置数の基準の点検・見直しを進めることなどを確認し、大規模イベントで女性用仮設トイレの十分な確保などを求める通知を主催者に発出。
これまで日本共産党の井上さとし前参院議員が国会で質問、23年5月の参院内閣委員会で、女性トイレを増やして行列を解消するよう提案、続いて24年、能登半島地震での避難所環境問題でトイレの緊急改善など政府に求めて来たもの。今動き始めています。
政府は同年12月の避難所の運営指針改定で、トイレの割合は男女比1対3を確保するよう明記しました。今年4月には、避難所で満たすべき基準は日常で当然必要となるとし、公共施設等の新改築の機会やイベント時のトイレの男女比を改善するよう要求。6月には、避難所になる学校の女性トイレの増設の考えを示しました。
知立市の今後の対応が大いに注目されます。