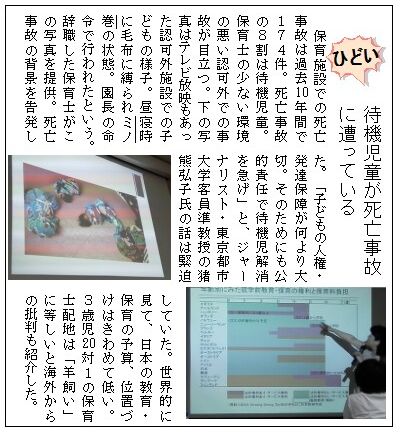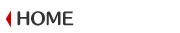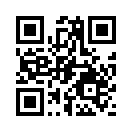市政の動き−議会報告
【16.09.03】《地方議員セミナーに参加》子ども・子育て支援新制度の下自治体における保育行政の課題は!
子ども・子育て新支援制度導入でも待機児童は減っていない
日本共産党市議団は8月3日、地方議員セミナーに参加しました。待機児童が全国で5万人といわれ、その解消が社会的注目の中、新制度がスタート。全国で小規模事業の進展はあるが3歳未満児の待機は減らず、新たに3歳児の壁が出現。セミナーでは4人の講師が新制度導入後の待機児童実態、解消をめぐる課題、保育士不足問題の解決のために等をテーマに講演された。

児福法第24条1項・保育所の公的責任を維持したことは貴重
子ども・子育て新支援法は、紆余曲折を経て、児童福祉法第24条1項を関係者の世論で守りぬき、保育所の公的責任が残った。2項で直接契約の認定こども園、小規模保育事業などが導入されたが、全国自治体が、申請窓口を自治体に一本化。これは評価すべき。
待機児は3歳未満児がほとんどだが、未満児保育を増やせば次に、3歳の待機児が出始めいたちごっこになる。やはり、認可保育園の増設が求められる。
「保育園落ちたの私。日本死ね」ブログきっかけに問題が浮上
ブログを契機に、大きな政治課題になった待機児問題。全園児が約1千万人で待機児数はその5%。やる気さえあればできる数字だと強調された。知立市の場合、
待機児童は今年8月時点で21名。全体の2%、まさに解決できない数字ではないはず。政府の調査で、妊娠中から「保活」が20%。行政は、待機児解消のため、保育士不足を一刻も早く解決すべきです。
週休2日の保障、事務時間確保、保育士確保に欠かせない要件
なぜ、若い保育士が5年未満で辞めていくのか。村山祐一元帝京大学教授は問いかけた。全国共通の現象であり、原因はアンケートなどでも明白。週休2日が確保されない、8時間保育の後の事務仕事等では自らの子育てが困難。辞めた保育士の再就職は幼稚園が多いことでも分かる。解決には、保育士配置基準の大幅改善、土曜日保育のシェア対応、夏季休暇の設定も必要と提案された。おおいに検討されるべき課題。国のさらなる規制緩和は事態を悪化させ、解決できない
ひどい!待機児童が死亡事故に遭っている