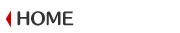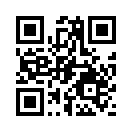市政の動き−議会報告
【15.01.23】《知立市議会》「(仮)手話言語法」の制定。認知症サポーター要請講座。
全議員が参加し、研修会を実施:「初めて知った」、驚きの声も!
知立市議会は1月16日、聴覚障害者のための「(仮)手話言語法」の必要性と制定後の影響等について知立市聴覚障害者協会会長 中島 宇月氏を講師に招き「手話言語法」についての研修を受けました。その後、知立市地域包括支援センター職員 酒井 佑氏より「認知症サポーター養成講座」を受講。いずれのテーマも今後の重要課題と認識しました。
「手話は言語である」障害者基本法に明記。
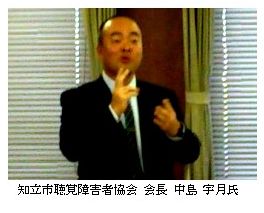 ろう者とは、耳が聞こえない人々のうち手話でコミュニケーションをとって日常生活を送る人達です。 手話は、ろう者にとってのコミュニケーション手段、物事を考えるための言語です。国連は手話を言語と認め、日本でも障害者基本法に明記しました。
ろう者とは、耳が聞こえない人々のうち手話でコミュニケーションをとって日常生活を送る人達です。 手話は、ろう者にとってのコミュニケーション手段、物事を考えるための言語です。国連は手話を言語と認め、日本でも障害者基本法に明記しました。
中島氏は、「日本のろう学校では、発音した口の形を読み取り、内容を理解する口話(こうわ)法教育が採用され、手話の授業がない。しかし、口形を見て話の内容を理解するのは困難」と説明。手話は、ろう者にとって社会生活を営むために必要な言語であり、早期の「手話言語法」制定が求められると熱く語りました。
講演を聴いた議員からは、ろう学校で手話が採用されていないことに驚きの声があがるなど、改めて手話の必要性を認識しました。
認知症サポーターとは。
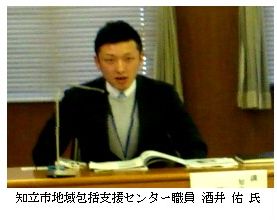 認知症は誰にも起こりうる脳の病気。65才以上では7人に1人。85歳以上では4人に1人が発症するといわれています。記憶障害や理解・判断力の障害などから不安に陥り、その結果、家族など周囲の人とのトラブルで双方が疲れきってしまいます。また、時間と場所がわからず、今、自分はどこにいるのか、なぜここにいるのか、昼なのか夜なのか、一種の迷子状態となり、不安が増大します。
認知症は誰にも起こりうる脳の病気。65才以上では7人に1人。85歳以上では4人に1人が発症するといわれています。記憶障害や理解・判断力の障害などから不安に陥り、その結果、家族など周囲の人とのトラブルで双方が疲れきってしまいます。また、時間と場所がわからず、今、自分はどこにいるのか、なぜここにいるのか、昼なのか夜なのか、一種の迷子状態となり、不安が増大します。
酒井氏は、「周囲の理解と気遣いで穏やかに暮していくことは可能であり、そんな時こそ認知症を理解し、本人や家族を見守る『認知症サポーター』の出番」と語りました。
サポーターは、様子のおかしい人を見たら、それとなく話しかけ、家族に連絡し、連係して、本人を落ち着かせ、家族の支援をします。地域での見守がサポーターです。