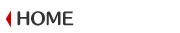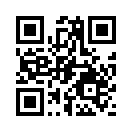【25.06.15】NO.2277 生態系生かす農業が日本の食守る 土は木以上に二酸化炭素を蓄える
自然の循環の仕組みこそ農業の基本 化学肥料・農薬を使わない農業を
 農業は単に食料の生産だけでなく、地球環境にも大きく影響します。食料の安定生産、供給を続けるには、日本の農地、風土にあった農業や経営の育成、所得補償、流通体制の整備が必要です。国も「みどりの食料システム戦略推進総合対策」として、環境と調和のとれた食料システムの確立に向け、様々な支援策を講じています。化学肥料や農薬を使わないことはもちろん、堆肥も使わないで、有機野菜を作る「菌ちゃん農法」が注目されています。
農業は単に食料の生産だけでなく、地球環境にも大きく影響します。食料の安定生産、供給を続けるには、日本の農地、風土にあった農業や経営の育成、所得補償、流通体制の整備が必要です。国も「みどりの食料システム戦略推進総合対策」として、環境と調和のとれた食料システムの確立に向け、様々な支援策を講じています。化学肥料や農薬を使わないことはもちろん、堆肥も使わないで、有機野菜を作る「菌ちゃん農法」が注目されています。
環境と調和のとれた農業 アグロエコロジー
アグリカルチャー(農業)とエコロジー(生態学)の2語を合わせた造語「アグロエコロジー」が
近年、世界で注目されています。読んで字のごとく生態系に沿った農業を指す言葉で、作物を育てるための土壌づくりに土中の微生物などの力を借りる手法です。農薬不使用はもちろんのこと肥料や堆肥、防虫作業も行わず野菜の栽培が可能になるのだという。植物は光合成で炭水化物をつくるが、その4割を土壌中に流す。その炭水化物で微生物を呼び寄せ、ミネラルを集め吸収しています。化学肥料でミネラルを与えると植物は微生物を呼び寄せる必要が無くなり、余分な炭水化物を出しません。微生物がいなくなると病気に弱くなり、農薬も必要になる。微生物のいる土壌で野菜を育てると、抗酸化作用を持つ成分が豊富な野菜ができ、虫も寄ってこない。
「菌ちゃん農法」とは
微生物の力だけで野菜をつくる「菌ちゃん農法」を実践して全国に広めているのが(株)菌ちゃんふぁーむ代表取締役の吉田俊道氏です。「菌ちゃん農法」は乾いた木や竹、ススキ、セイタカアワダチソウなどの硬い雑草やもみ殻を土中に埋め込んだ高畝を作り、適度の水分でキノコやかびの仲間である糸状菌を増やします。菌の力で、炭素分を多く含んだ有機物を分解して養分やエネルギーを効率よく野菜に与えます。糸状菌が土壌中に広がり、土が耕されると、野菜と相性の良い菌が根に侵入して、共生関係を結びます。こうした菌が多い畑の野菜(元気野菜)は、虫に食べられず、病気にも強く、連作障害も減るという.

元気野菜は 人間の体も元気にする
糸状菌などの多い畑の野菜は「第7の栄養素」と呼ばれるファイトケミカルやミネラル、ビタミンが豊富になります。ファイトケミカルはリコペンやイソフラボンなど野菜や果物などの植物が持つ成分の総称で抗酸化作用を持ち、植物自体が身を守る為に生み出している色素や苦み、辛みといった部分に多く含まれています。元気野菜を食べると体の中にビタミンやファイトケミカルも取り込まれ病気に対する抵抗力、回復力を増進させます。
剪定枝は焼却ではなく、 チップ化して土に返そう
 知立市からクリーンセンターに搬入された木・竹は年間約4600トン(令和5年度)で全量焼却しています。焼却により大量のCO2を排出しています。このクリーンセンターに持ち込まれる木や竹の一部分でもチップ化して、有機野菜を作る農家や、家庭菜園で野菜を作る市民に提供すれば、CO2を削減し、循環型農業の支援になります。クリーンセンターに持ち込まれる量が減れば、知立市の環境組合負担金も減少します。チップ化する場所や設備の確保には「みどりの食料システム戦略推進総合対策」の交付金活用も可能ではないでしょうか。
知立市からクリーンセンターに搬入された木・竹は年間約4600トン(令和5年度)で全量焼却しています。焼却により大量のCO2を排出しています。このクリーンセンターに持ち込まれる木や竹の一部分でもチップ化して、有機野菜を作る農家や、家庭菜園で野菜を作る市民に提供すれば、CO2を削減し、循環型農業の支援になります。クリーンセンターに持ち込まれる量が減れば、知立市の環境組合負担金も減少します。チップ化する場所や設備の確保には「みどりの食料システム戦略推進総合対策」の交付金活用も可能ではないでしょうか。